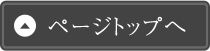無花果はクワ科イチジク属の落葉樹。赤紫や緑の実の中には、ぷるんとした赤い果肉とプチプチの種が詰まっていて、ひと口食べると、やさしい甘さと独特の香りが口いっぱいに広がります。日本ではちょっと地味な存在かもしれませんが、実はとても古い歴史をもつ果物。ピラミッドの壁画や旧約聖書にも登場し、宗教や文化の象徴として世界中で大切にされてきました。
■古代から人々に愛された無花果
無花果の原産地は中東のメソポタミアや地中海沿岸。世界最古の栽培果樹のひとつとされ、オリーブやブドウと並び、古代文明に欠かせない果実でした。
旧約聖書では、アダムとイブが禁断の果実を食べて羞恥心を覚え、体を隠すのに使ったのは無花果の葉だったとされています。禁断の実はリンゴではなく、無花果だったとする説もあります。
古代エジプトでは「生命の木」として神聖視され、ミイラの副葬品に入れられたり、ピラミッドの壁画に描かれたりしました。
・日本に伝わった当初の呼び名は「唐柿」「南蛮柿」
日本への伝来は、16世紀ごろに中国から伝わったといわれています。最初は観賞用・薬用として広まり、「唐柿(とうがき)」「南蛮柿(なんばんがき)」などと呼ばれていました。その後、江戸時代に食用が広まり、明治時代には本格的に栽培が始まります。
■無花果には花がない?「無花果」の名前の由来
「無花果」という漢字は「花がない果物」という意味。でも実は、花は果実の中に隠れて咲くので外から見えないのです。そのため「花がない」と思われて名付けられました。
「いちじく」という名前の由来には、ほかにも説があります。
• 1か月で熟すことから「一熟(いちじゅく)」がなまった説
• 中国名の「映日果(インリークォ)」の唐音読み(えいじつか)が変化した説
• 異国から来た珍しい果物という意味の「異知菓(いちか)」からきた説
どれもユニークですね。
■栽培の中心は西日本
現在、日本で多く栽培されている品種は2タイプ。 「夏秋兼用型」 と 「秋果専用型」 です。
・夏秋兼用型:6月頃に「夏果」、8〜10月に「秋果」が収穫できます。やや小ぶりで、風味が素朴。品種では「蓬莱柿(ほうらいし)」などがあります。
・秋果専用型: 8〜10月に一斉に収穫されます。果実が大きく甘みが安定していて市場流通に適しています。品種では「桝井ドーフィン」「バナーネ」などがあります。
栽培は愛知・和歌山・福岡が三大産地で、和歌山県が全国トップの収穫量を誇ります。
■ブランドいちじくと加工品
近年は高級フルーツや加工品としての需要が増加しています。近年はブランド化も進み、「安城いちじく(愛知)」「紀の川いちじく(和歌山)」「とよみつひめ(福岡)」などが有名です。
生で食べる以外にも、ジャムやコンポート、ドライフルーツ、お菓子やパンの材料などに利用されます。ただし加工用は日本産よりもトルコやイランからの輸入品が多くなっています。
■おいしい無花果の選び方
・色が全体にムラなくついている
・ふっくら丸みがある
・軽く触るとやや柔らかい
・お尻の部分が割れかけていると完熟
これらが熟している証拠です。追熟しないので、買ったらなるべく早く食べましょう。
■食べ方いろいろ
皮をむいてそのまま食べるのはもちろん、サラダやヨーグルトにトッピングするのもおすすめ。生ハムやクリームチーズと合わせると、おしゃれな前菜になり、ワインにもぴったり。はちみつをかければ簡単スイーツに。皮の薄い品種なら、皮ごとおいしく食べられます。
2025年09月12日