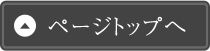10月8日は二十四節気の「寒露(かんろ)」。草木に冷たい露が降りる頃という意味です。朝晩はひんやりと冷え込むようになってきましたね。
七十二候では「鴻雁来(こうがんきたる)」に入ります。4月10日頃の「鴻雁北(こうがんかえる)」と対になり、北の方から雁が再び渡ってくる頃です。
北方の厳しい寒さを逃れて秋から冬に海を越えて渡ってくる渡り鳥を「冬鳥」と言います。日本で見られる冬鳥は雁の他、ハクチョウ、ツル、カモ、ツグミなどがいます。冬鳥は、アラスカ、シベリア、カムチャッカなどで、短い夏の間に卵を産み、子育てをします。そして餌場が雪や氷で閉ざされる頃、冬でも餌の多い南へ向かって渡ってきます。
「雁行」とも呼ばれる雁などのV字飛行は有名ですね。V字になって飛ぶことで、前方の鳥の作る気流に乗ることができ、効率良く飛び続けることができるのだそうです。
10月の寒露の頃、近くを通るとふいに香ってくる甘い香りで「あ、金木犀が咲いているな」と気が付くことがあります。金木犀は、その姿より先に香りで気づかれるほどの豊かな芳香が特徴で、梔子(くちなし)、沈丁花(じんちょうげ)とともに「三香木(さんこうぼく)」と呼ばれています。中国原産で金木犀の名前の由来は、樹皮が動物のサイ(犀)の皮に似ていて、金色の花を咲かせるからといわれています。いつ頃から木犀と呼ばれたのかはわかりませんが、その当時サイをどこでみたのか、ちょっと不思議。金木犀の意外なまめ知識をご紹介しています。
【暮らしのまつり・遊び】秋/金木犀
2025年10月08日