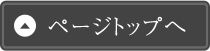10月18日からは七十二候の「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」。秋の虫が戸口で鳴く頃という意味です。今は「蟋蟀」を「こおろぎ」と読みますが、昔は「こおろぎ」のことを「きりぎりす」と呼びました。
俳句で「虫」と言えば、秋に草むらで鳴く虫たちのことを指す、秋の季語です。
虫の声が幾重にも重なって賑やかな様子を表す「虫時雨(むししぐれ)」や「虫集く(むしすだく)」、暗闇に虫の声だけが聞こえる「虫の闇」、昼間でも鳴いている「昼の虫」など、「秋」の風情を表す言葉もたくさんあります。
テレビを消して、耳を澄ましてみては?家のまわりでも、小さな音楽家たちの演奏会が始まっているかもしれません。
さて、一年中、気軽に食べられる蕎麦ですが、蕎麦は、夏と秋に収穫され、夏の新蕎麦を略して「夏新(なつしん)」、秋の新蕎麦を略して「秋新(あきしん)」と呼びます。蕎麦も実りの秋に収穫されたものが一番おいしいといわれ、蕎麦好きな人たちが心待ちにしている新蕎麦です。
その蕎麦の味わい方ですが、蕎麦はもともと皿に盛り付けた「もり」蕎麦で、その後冷たいつゆをぶっかけた「かけ」が現れ、寒い時期に温めたつゆをかけるようになりました。やがて、蕎麦を盛り付ける器によって「ざる」と言ったり「せいろ」と言ったり、海苔がかかったりとさまざまに変化して、今ではお店によってもまちまちです。蕎麦にはこだわりを持つ人も多いもの。皆さんは「もり」派ですか?「かけ」派ですか?
【季節のめぐりと暦】七十二候
【暮らしのまつり・遊び】秋/虫の声・鈴虫の飼い方
【旬の味覚と行事食】秋/新蕎麦
2025年10月18日