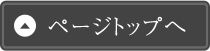熱い日差しが注ぐ夏、見上げると青空に白い雲がいくつも浮かんでいます。「夏の雲」といえば「入道雲」「わた雲」「雷雲」「かなとこ雲」などがあります。夏にだけみられるわけではありませんが、夏に発生しやすい雲です。雲を見ると天気の変化を予想することもできます。天気の急変も多い夏、夏の雲のまめ知識を知っておくといいですね。
■わた雲:積雲(せきうん)
青空に浮かぶ白い綿のような雲は「わた雲」。正式名は「積雲」です。
気象学では、空を高い方から順に上層・中層・下層と呼び、上層は高度5,000~1万3,000m、中層は高度2,000〜7,000m、下層は高度2,000m以下としています。空のどの高さで発生した雲なのかによって、大まかに上層雲、中層雲、下層雲に分けられます。
「わた雲」は、地上から2,000m以下の下層にできる雲ですが、気温の上昇によってどんどん大きくなると上層まで届くような入道雲に発達します。
■入道雲(にゅうどうぐも):積乱雲(せきらんうん)
夏の雲といえば、空高く立ち上がる「入道雲」。正式には「積乱雲」といいます。
気温が高いと上昇気流が発生し、低層にあったわた雲がどんどん大きくなって入道雲となり、高さ1万メートル以上に達することもあります。
夏は午前中に地面が熱され、午後に上昇気流がピークになるので、午後2時ごろからが最も入道雲が発達しやすい時間です。 雲の成長を観察してみるのも面白いですね。
入道雲の「入道」とは仏門に入った人のことで、雲の形がその坊主頭に似ていることが名前の由来とされていますが、坊主頭で大きな体の妖怪「大入道」のようだからという説もあります。
空の怪物のように大きい入道雲は、夕立や雷を引き起こす原因になりますので要注意です。
■雷雲(かみなりぐも/らいうん):積乱雲
暑い日でも積乱雲の上層部は-20℃以下になることもあります。雲の中では氷の粒や水滴がぶつかり合って静電気が起き、この静電気がたまって雷が発生します。
積乱雲が発達して雷雲になり、黒い雲が現れ急に暗くなったり、涼しい風が吹いてきたりしたら要注意です。雷や急な豪雨のほか、突風が吹いたり、雹が降ったりすることもあります。
■かなとこ雲:積乱雲
積乱雲が上へと発達し、上空の圏界面(対流圏と成層圏の境目)にぶつかると、雲はその上にはいけないので上部が平らに広がった巨大な雲になります。鉄などを打つ時の台である「鉄床(かなとこ)」のようなので、「かなとこ雲」と呼ばれます。
分厚いかなとこ雲の下は暗くなり、気温が急に下がり、雷やゲリラ豪雨、突風や竜巻が起こるなど危険ですから、注意が必要です。
■台風は巨大な積乱雲の渦
夏から秋にかけては台風シーズンでもあります。台風も巨大なエネルギーをもった積乱雲で形成されています。
熱帯の海上で上昇気流によって水蒸気が吸い上げられ、次々と積乱雲が生まれ、それらがまとまって渦を巻くようになります。水蒸気をエネルギー源として発達し、渦の中心付近は気圧が下がり熱帯低気圧となります。さらに発達して風速が秒速17 mを超えるものを台風と呼びます。
台風が日本のほうへ近づいてくるのは、日本の東側にある太平洋高気圧のため。もともと低気圧の台風は高気圧の壁に阻まれて、高気圧の外側を回るように動きます。さらに偏西風の影響で東へ進路を向け、日本に近づいてくることが多くなるのです。
抜けるような青空に、ぽっかりと白い雲。さわやかな夏の景色は美しいものですが、地球温暖化で世界的に猛暑となっている昨今、気象情報にも注意を払いたいものです。
2025年07月28日