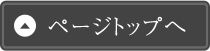11月の和風月名は「霜月(しもつき)」。旧暦の11月は今の12月頃にあたります。文字通り、霜が降る月ということで「霜降月(しもふりつき)」が略されて「霜月」となりました。木の葉などの露が凍って霜になり、消えてしまうので「露隠月(つゆごもりづき)」「露隠葉月(つゆごもりのはづき)」ともいわれます。
11月2日は旧暦9月13日にあたる「十三夜」。十三夜の月は、「後(のち)の月」とも呼ばれ、十五夜に次ぐ名月とされています。十五夜または十三夜のどちらか一方のお月見しかしないことを「片見月」「片月見」と呼び、縁起が悪いともいわれています。
十三夜は、栗や豆の収穫祝いでもあったため別名「栗名月」「豆名月」といい、栗や枝豆を供える習わしがあります。名月を眺めながら栗ごはんや豆料理で食欲の秋を堪能するのも良いですね。
また、2日は「亥の子の日」でもあります。本来は亥の月(旧暦10月)の最初の亥の日のことをいいますが、現在は一般的に新暦11月の最初の亥の日で考えます。亥の子の日には、西日本では「亥の子祭り」という収穫祭が行われ、「亥の子づき」をしたり、亥の子餅を食べたり、こたつ開きをする習わしがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
【暮らしのまつり・遊び】冬/亥の子
東日本では、亥の子まつりに似た行事として11月10日(本来は旧暦10月10日)の「十日夜」があります。十五夜、十三夜と並んで3月見のひとつでもありますが、収穫に感謝する祭りの意味もあり、中には「かかしあげ」といってかかしにお供えものをしてお月見をさせてあげる地方もあります。
【季節のめぐりと暦】和風月名
【暮らしを彩る年中行事】お月見(十五夜・十三夜・十日夜)
【暮らしのまつり・遊び】冬/亥の子
2025年11月01日