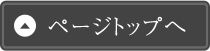11月12日から、七十二候では「地始凍(ちはじめてこおる)」になります。大地が凍りはじめる頃という意味で、霜が降りたり、霜柱が立ったり、水たまりに氷が張ったりしはじめます。11月に入り、朝晩はけっこう冷えるようになりました。地域によっては、霜が降りるところもあるでしょう。アスファルトばかりの都会では霜柱を踏む機会もありませんが、子どもの頃、霜柱を踏んだ時のあのサクッとした感触がなんとも気持ちの良かったものです。
さて、今日は鷲(おおとり)神社など、日本武尊(やまとたける)をまつる神社で酉の市が開かれます。酉の市は11月の酉の日に開かれる露天市で、大酉祭(おおとりまつり)、お酉様(おとりさま)などともいわれます。熊手や招き猫などの縁起物を買い、一年の無事と来る年の福を願います。酉の日は12日ごとにめぐってくるので、2025年は11月12日が一の酉、11月24日が二の酉となります。
そして、11月15日は「七五三」。子どもの健やかな成長を願い、男の子は3歳と5歳(5歳のみ行うところも多いです)、女の子は3歳と7歳のときに晴れ着を着せて神社に参拝し、人生の節目を祝う通過儀礼です。
七五三は、もともとは公家や武家で行われていた「髪置き」「袴着」「帯解き」という別々の儀式でした。それが江戸時代後期に1つになり、その後、今のような形になって広まりました。昔は「7歳までは神のうち」といわれるほど子どもの死亡率が高く、子どもを無事に育てるのは大変だったため、節目節目に神様に感謝をして、健やかな成長を祝うようになりました。
【季節のめぐりと暦】七十二候
【暮らしのまつり・遊び】冬/酉の市
【暮らしの作法】人生の通過儀礼/七五三
【暮らしの作法】人生の通過儀礼/子どもの通過儀礼
2025年11月12日