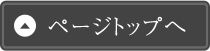5月5日は「立夏」。そして「こどもの日」「端午の節句」です。
二十四節気では、立夏から立秋の前日までが夏です。今年も4月に気温が30℃以上の真夏日になる地域もあり、一足早く夏を感じるような日もありましたが、晴れればさわやかな新緑の季節です。
田んぼでカエルが鳴き出すのもこの頃。七十二候では「蛙始鳴(かわずはじめてなく)」になります。田んぼに水が入れられ、田植えがはじまる頃、夜になると蛙たちがいっせいに鳴きはじめます。
さて、「こどもの日」として知られている端午の節供は、五節供の一つ。古代中国から伝わった「端午」の行事は、日本で「端午の節供」となり、その意味や祭りは長い間に幾度も変化し続けてきました。あるときは、皆のために。またあるときは、乙女のために。そして現在は子どもたちのために。端午の節句の由来はこちらをご覧ください。
【暮らしを彩る年中行事】五節供/端午
こどもの日の風物といえば「鯉のぼり」。5月の空に悠々と泳ぐ姿は壮観です。都会ではあまり見かけられなくなりましたが、マンションのベランダなどにかわいらしい鯉のぼりが泳いでいるところもありますね。
鯉のぼりを揚げるのは、江戸時代、男の子が生まれた印として幟(のぼり)を立てた武家をまね、粋な町人たちが和紙で作った鯉の幟を揚げたのがはじまりです。鯉は立身出世のシンボルで、鯉が滝を昇って龍になったという「登龍門」伝説に由来します。
このほか、「菖蒲湯」で厄除けしたり、「粽(ちまき)」や「柏餅」を食べたり、さまざまな風習が続いていますが、なぜでしょう? それぞれの由来や、豆知識もご紹介しています。
【暮らしの知恵】暮らしのヒント/菖蒲湯
【旬の味覚と行事食】春/粽・柏餅
【季節のめぐりと暦】二十四節気/立夏
【季節のめぐりと暦】七十二候
【暮らしのまつり・遊び】春/アマガエル
2025年05月05日